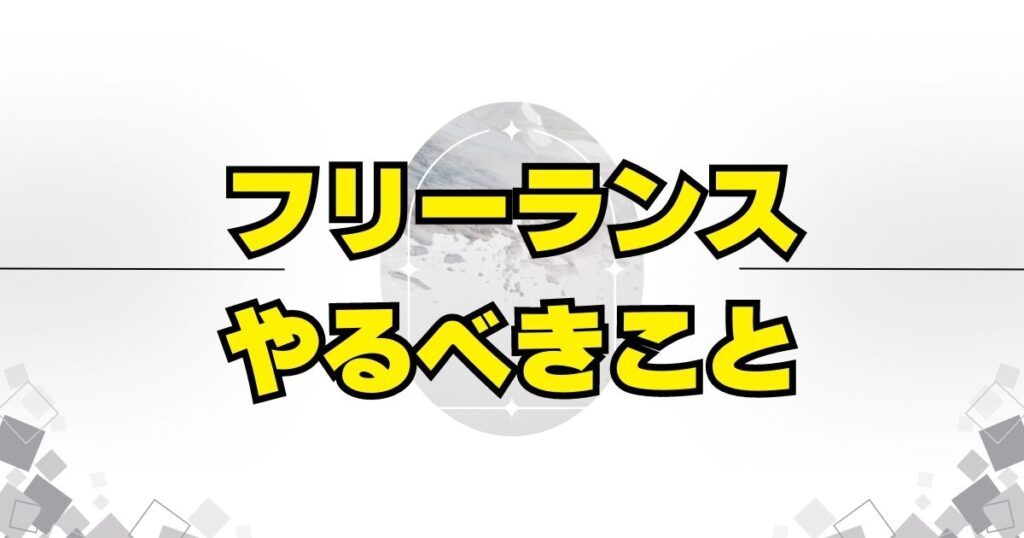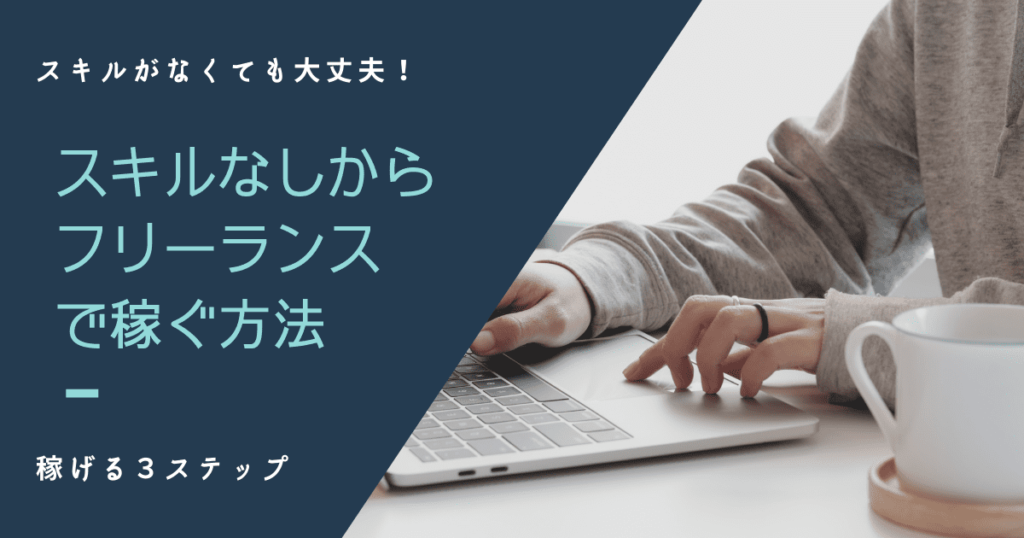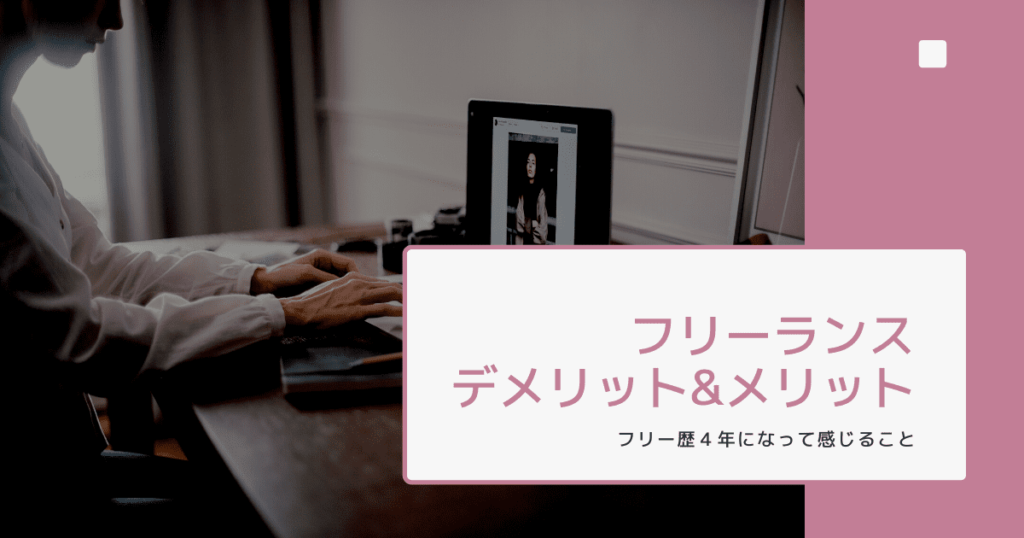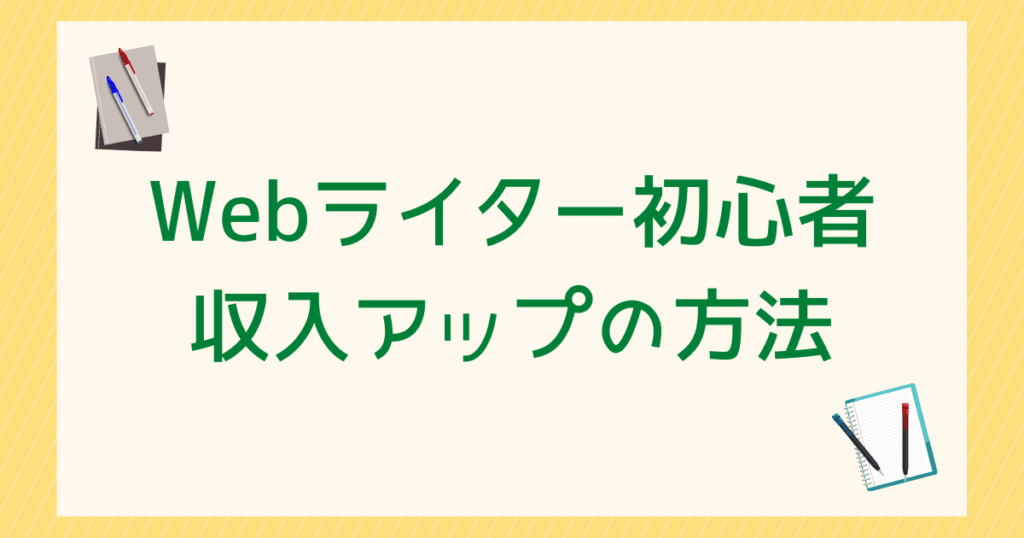- セルフブランディングをするときは「3つのポイント」を理解しておきましょう。
- ブランディングには「時間的要素」を考慮しての活動が大切です。
- ブランドが強固になれば、マーケティング活動が不必要になります。
今回のテーマは『フリーランスのセルフブランディング戦略』について!
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
「ブランディング」とか「ブランド」って聞くと企業や商品をイメージしがちですが、実はフリーランスにとっても大切なことなんです。
わたしはフリーランスになって約6年が経ちますけど、いまでもセルフブランディングについては日々考えながら活動しています。
フリーランスや個人事業主がブランディング戦略をするにあたり、日々の「情報発信」は欠かせないもの。
だけど以下のように、身の丈に合わないことばっかり発信してると、逆にブランディングって失敗するんです。
- タワマンでのパーティ
- 有名人との2ショット
- キラキラ女子会 etc
こういった自分を大きく見せたいための投稿、これって「セルフブランディング失格」だなって思います。まさに逆効果。
そこで今回はフリーランス目線から、ブランド構築に必要な「3つの視点」や「ブランディングのメリット」について解説していきます。
こちらの動画ではポイントを深掘りして解説しているので、ぜひ併せてご覧ください(「高評価・チャンネル登録」お願い致します)。
セルフブランディングに必要な3つの視点
まずはじめに、ブランディングに大切な「3つのポイント」を押さえておきましょう。
このポイントを押さておかないと、SNSとかでもよく見かける「痛いヤツ」って思われてしまう、そんなセルフブランディングになってしまうから。
ブランド構築に重要となるポイントは、以下の3つです。
- 機能的価値:商品やサービスの性能、機能
- 感情的価値:商品やサービスの好感度
- 他者からの心象:販売者、商品、サービスのイメージ
ちょっと難しく感じるかもしれませんが、この3つのポイントを意識しておくことで「確固たるブランド」が構築できます。
また、フリーランスが「セルフブランディング」をするときは、以下のように置き換えると分かりやすいです。
- 機能的価値:専門スキル、他者より優れた点、実績
- 感情的価値:口コミ、評判、他者からの推薦
- イメージ:身なり、口調、態度、肩書き
これら3つのポイントについて、もう少し具体的に掘り下げていきましょう。
機能的価値としての自分をアピール(視点①)
まずは「自分が優れているポイント」を積極的にアピールしていくことが大切です。いわゆる、専門性、長所、特長、実績など。
たとえば、以下のように「専門分野に関する知識」だったり、あるいは「自分が得意なこと」だったり、周りの人たちが価値を感じてくれることを発信していきましょう。
- Webデザインに関する知識
- YouTubeのノウハウ
- 料理のテクニック
フリーランスの活動に関することで「自分がアピールしていきたい」ものを1つに絞り、ブログ、YouTube、SNSなどで情報発信してみてください。
そして、さらに大切なことは、これら知識とかノウハウ、テクニックなどを「日々アップデートしていく」ことです。
- 自分の好きや得意を発信する
- インプットして知識を高める
- 実践しつつスキルや経験を得る
- 得たことをさらに発信していく
上記のような作業を繰り返しながら、いわゆる「機能的価値としての自分」を高めていくだけ。これがフリーランスの情報発信です。
さらに言うなら、周りの人たちの「予想を超えるもの」を発信できるようになったら、それだけで自分の「価値」とか「存在感」っていうのは勝手に高まっていきますよ。
感情的価値(情緒的価値)を高めていく(視点②)
ブランディングをしていくには「機能的価値」を高めることも必要なんですが、さらに「自分を好きになってもらう」ことも大切です。
いくら価値ある情報を発信していても、やっぱり「アイツはなんか好かん」と思われてしまったら、ブランディングの足を引っ張ってしまうので(いわゆる好感度が低い)。
ちなみに、次のような職業の人たちって「感情的価値の高め方」がめちゃくちゃ上手いです(人からの好かれ方が上手)。
- アイドル
- タレント
- YouTuber
でも「人に好かれよう」って言われると、なんだか難しく感じちゃいますよね。
そんなときは、まず「知的正直さ」というものを大切にしながら発信していけば大丈夫!
少しずつ周りから信用してもらえるようになっていくので、やがてそれが「好かれる」とか「惹かれる」につながっていくので。
知的正直というのは簡単に言えば、わからないのにわかったふりをしない、ということにつきるのである。
『知的生活の方法』より引用
- 自分を誤魔化すのではなく、自分が知識を持たない、即ち知らないということを認める正直さ
- わかったふりをすると進歩が止まる
- 渡辺昇一名誉教授「知的生活の方法」で触れられている
つまり、知的正直さを持っていれば「知ったかぶりをしなくなる」とか「素直にわからないと言える」とか「もっと知ろうと努力する」など、周りから信用される行動を取れるようになっていきます。
もちろん、取引先との関係においても「知的正直さ」とか「素直さ」ってとても大事。これが無いと仕事がもらえません。
こういった行動が、取引先からの良い評判とか口コミに繋がっていくんですよ。
どういうイメージを持たれたいか(視点③)
セルフブランディングにも、いわゆる「イメージ」というものも大切で、たとえばこんな感じです。
- 知的で誠実さが溢れている
- 明るく楽しくて親しみやすい
- 真面目でとても落ち着いている
つまり、周りから「どう見られたいか」をしっかり決めておくと良くて、いわゆる「キャラクター」とか「世界観」とか「人柄」といったものを意識してください。
こういうことって、常日頃から意識して情報発信をすることが大切で、イメージというのは「時間をかけて定着」させていくものだからです。
そして、以下のような「インターネットを使った情報発信」というのは、ブランディングには欠かせないスキル。
- SNS
- ブログ
- YouTube
しかもこれらのツールは、ブランディングに役立つだけでなく「効率よくお金を生み出してくれるツール」でもあります。
まさに「誰でも」セルフブランディングができ、しかも稼げてしまう。ホント便利な世の中になりました。
セルフブランディングでは「時間的要素」も重要
ここまで、セルフブランディングをしてくために必要な3つのポイントをお伝えしてきましたが、ここからは「時間的な側面」についても触れていきたいと思います。
ブランディングには「時間的要素」が大きく関わってくるので、ぜひ以下の視点も持っておいてください。
- 長期的視点
- 短期的視点
この2つの視点には、それぞれメリットとデメリットがあります。
| 時間的要素 | 方法 | メリット | デメリット |
| 長期的視点 | 自分(数年~数十年単位) | 強固なブランディング | 途中であきらめてしまう |
| 短期的視点 | 他者の紹介 | 即効でブランディング | 実力がないと逆にマイナス |
※タップして横スクロールで全部見れます
結局のところ、長期的視点と短期的視点を「併せ持った」ような戦略を考えておくことが大切で、いずれ他者から紹介されるよう「まずはコツコツと自分でブランディングしていく」のがベストです。
たとえば、フリーランスなら仕事に繋がるようなブログを書いていると、徐々にブランディングが形成されて仕事も入るようになってきますよ。
ブランディングしていくことのメリット
それでは最後に、セルフブランディングで得られるメリットについて紹介していきます。
まず、ブランディングをすることで得られる「ブランドの恩恵」は、以下のようなことです。
- ライバルと比較されなくなる
- 商品やサービスが簡単に売れる
- 商売や収入が安定してくる
- 「真のファン」ができる(逆風でも応援してくれる)
- 「顧客のストレス」を軽減できる(頼りにされる)etc
このようなメリットがあり、ブランド力が高まれば高まるほど「大きな影響力」を持つこともできます。
ただ、こういったメリットがある反面、逆に気をつけておくべきこともあって、それを無視すると「ブランドの崩壊」につながってしまいます。
- 「悪い意味」で期待を裏切ったとき
- 今の自分を捨てて、新しいステージに移ったとき
当然ですが「悪い意味」で期待を裏切ってしまったり、期待を裏切り続けてしまうと、ブランディングは崩壊していって再起は難しくなってしまいます。
逆に、活躍するステージが変わったときもブランドが崩壊するので、再び「新しいブランド戦略」を立て直さなければなりません。たとえば、以下のような場合に。
- アイドルを卒業して女優に転身
- フリーランスから株式会社を設立
- ラーメン屋をたたんでカフェを開店
これらは一例ですが、もちろん「新しいステージに合わせた」セルフブランディングをしていく必要があります。
そして、ブランディングが強固になればなるほど「売り込み」をしたり「マーケティング」をする必要もなくなって、勝手に売れていく「無敵モード」に突入するんです!
といことで最後になりますが、しっかりとした「セルフブランディング」ができれば、後々になってかなり楽になりますから、まずはコツコツ頑張っていきましょう。